第70回小学校中学年の部 優秀作品
「ぼくの中にバッハがいた!」
横浜市立山内小 4年 野本拓真
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
やったあ。夏休みの初め、パイプオルガンの演そう体験ができることになった。
パイプオルガンは、ホールのかべいっぱいに色々な大きさや太さ、素材のパイプが並べられていて、その一つひとつに風を通して音を出す楽器。楽器の王様ともよばれている。
ぼくが弾きたいのは、バッハの「五つの小プレリュード第一番BWV九三九ハ長調」だ。ピアノで弾いても美しい曲だけれど、最初の3小節の持続低音はピアノだとその仕組み上、だんだん音が小さくなっていってしまう。バッハがこの曲を作曲したときと同じパイプオルガンで弾いたら、どんな音がするんだろう。そんなことを考えながら当日をむかえた。
想ぞうしていた音とまったくちがった。せん細なのにはく力もある安定した一音一音が背中からぼくの中に入ってきて、体がふわっと持ち上がるような感覚だった。
天井近くまで届く一本一本のパイプからホール全体の空気をふるわせて、音がぼくの中にいる想ぞうのバッハを見つけに来た。
この本は、音の性質や音が聞こえるまでの仕組みをわかりやすい絵と合わせて教えてくれる。3年生の時の理科の授業で音の伝わり方を学んで、音の正体が空気のふるえだということは知っていた。しかし、それが耳に入った後、どうやって音として聞き取れるようになるのかは知らなかった。耳には「蝸牛」というカタツムリのような形をした器官がある。そこに生えているうぶ毛のようなものがゆれて電気信号が作り出され、それが脳に伝わると音として聞こえるようになるなんて、耳も脳もすばらしい働きをしている。図かんによると、このうぶ毛のようなものは「コルチ器の有毛細胞」とよばれているそうだ。
「ステレオこうか」という言葉も初めて聞いた。左右の耳がそれぞれ受け取る音のタイミングと大きさにはズレがあり、それをもとに脳が音の向きや距離などを正確に計算することで、立体感のある音が聞こえているということにおどろいた。また、ホールのかべや天井からはね返った音のひびきには、体を包みこむこうかもあるらしい。そうだとすると、ぼくがパイプオルガンを弾いたときに感じた体がふわっと持ち上がるような感覚もステレオこうかによるものだったのかもしれない。
しかし、「ぼくの中にバッハがいた」ことをステレオこうかだけで説明することは難しいな。そう思ってこの本を読んでいると、最後のページに「音には、目に見えないけしきだってイメージさせる強い力がある」と書いてあった。
この一文にはっとした。
パイプオルガンの音は、ぼくの想ぞう力を自由にかきたてて、今までぼくの心の中にいるなんて気がつかなかったバッハをたしかに見つけに来た。
これからもたくさんの色々な音と出合い、ぼくの中にあるまだ知らないけしきが見えてくるのが楽しみだ。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
●読んだ本「聞いて 聞いて! 音と耳のはなし」(福音館書店)
髙津修、遠藤義人・文 長崎訓子・絵
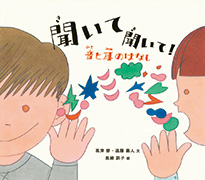
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
※無断での転用・転載を禁じます。
